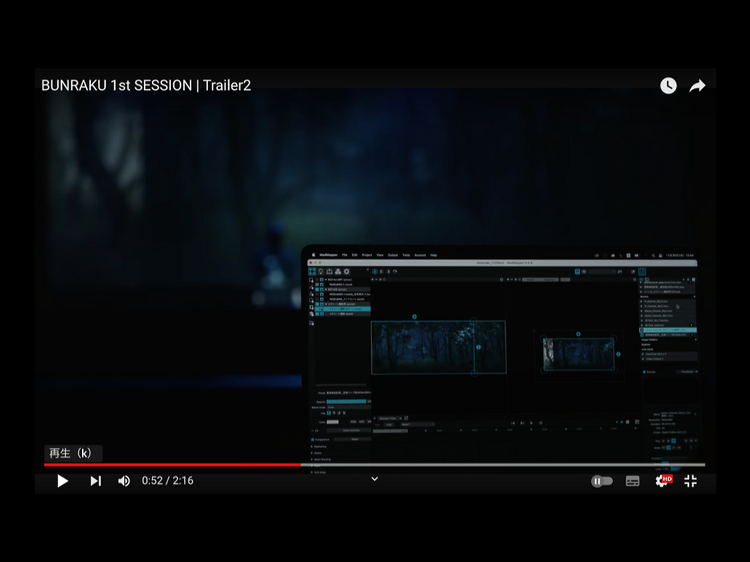イメージを練り上げて背景画を依頼


映像作家・山田晋平に聞く Vol.1
これまで、現代劇、コンテンポラリーダンス、オペラ、バレエなどさまざまな舞台芸術の映像を手がけてきた山田晋平は、今回の企画の初期段階から大きな役割を果たしているキーパーソンの一人だ。
「私が劇場のプロデューサーの方から今回のお話をいただいた時、男鹿さんに話は行っていたけれど、作業の内容や分量がわからないと返事ができないと言われていました。そこで僕が男鹿さんに引き受けてもらうための具体案を作ることになったのです。
そのために床本(ゆかほん)や過去の映像で勉強したほか、国立劇場の美術スタッフの方からこれまでの美術の資料を見せていただいて。その結果、従来の「曾根崎心中」の書割(舞台背景)でも、町のようなものが描かれた時代もあれば森の中から始まる時代もあり、川が描かれた時代もあれば橋だけで表現した時代もある、といった変遷があることがわかりました。
また、男鹿さんの絵にはさまざまな魅力があるので、画集を見ながらどこを出していただけるかということも考えました。今回、映像監修を務める桐竹勘十郎さんから『男鹿さんは自然の造形物が素晴らしい』とうかがって、なるほど、と。
そうしたことを全て考慮した上で、男鹿さんには大きくは4つのシーンをお願いすると決め、絵コンテのようなものをお渡ししたところ、『それなら、自分一人でできます』と快諾くださいました」
そこからさらに、イメージをすり合わせる作業を行った。
「時間は何時ごろなのか、木の枝ぶりはどうなのか、森の中から空は見えるのか、など、男鹿さんが描きやすいよう、細かい情報を決めていきました。男鹿さんが描かれるのは4シーン分で、僕がそれに新たなものを付け加えることはないのですが、横に長い絵を描いていただいて登場人物と一緒にスライドして使用するところもありますし、人魂などを動かすところもあります。
ただ、映像でなければできないことをやる瞬間は限定しようと考えています。今は、足し算よりも引き算を考えている段階。文楽は基本的にはやっぱり、人形を見る芸術ですから」