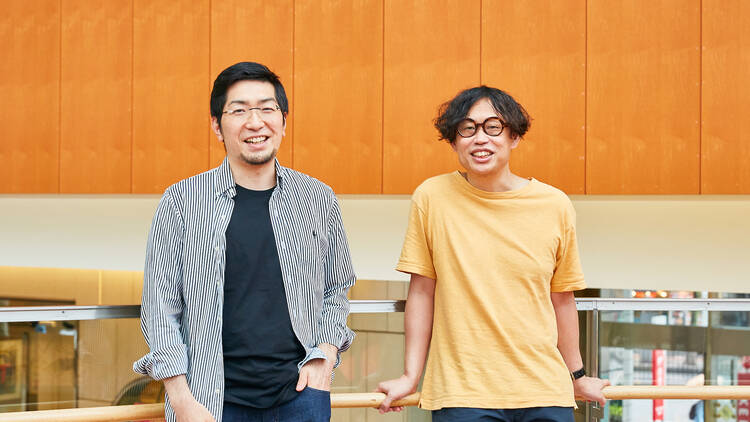ー右近さんの研の會も今年で7回目を迎えます。
右近:僕は初め、「やりたい役をやれるタイミングがいつか分からないから自分でやっちゃう」という感じでしかなかったんです。第1回でやったのが、歌舞伎に憧れるきっかけになった映像で曽祖父が踊っていた「春興鏡獅子」。これを得意演目になさった先輩方を見ると、「初役」、つまり初めてその役を務めるということを20代前半のうちに経験しています。
でも僕のように好きで役者をやらせてもらっている立場では、それがいつになるのか見えない。生涯「鏡獅子」を踊り続けたいと思っている身としては、出遅れてしまう。実際、僕はまだ歌舞伎の本公演で鏡獅子を踊ったことがありません。だから自主公演として自分でやることにしたんです。
ところが、自主公演をやっている先輩たちから「やるからには続けなさい」「回数を重ねないと意味がない」と言われ、「じゃあ来年は何にしよう」と考えながらやりたいものを続けているうち、徐々に世の中も、そして歌舞伎や自分の状況も環境も変わってきて、自主公演をやる意味やコンセプトにもおのずと変化が出てきました。
坂入:どう変わってきたんですか?
右近:最初のうちは「やれるかどうか分からないからここでやるしかない」という場所だったのが、歌舞伎の本公演で真ん中に立たせてもらうことも少しずつ増えてきて、今は逆に「自主公演でしかできないものにこだわるべきだ」という気持ちになったり、「歌舞伎の本公演でやりたいと思っているものをまずやらせてもらう場」になったり。
そうやって毎年、その時期になったら周りを巻き込んで大変な思いをさせてやっているのですが、それが一つの流れになって慣れが生まれてくると飽きてしまう部分がある。だから先ほど「飽きないですか?」と伺ったんです。
坂入:ああ、めちゃくちゃ分かりますね。流れ作業だとか停滞が見えた瞬間に、芸術的なものはどんどん落ちてくる。だから「あ、これ慣れてきたな」って思ったらもう全然別のことをやったりします。本来向かうところとは違うアプローチをあえてしたり、アマチュアのオーケストラだけれども全然違う音を持ったプロを入れてみたり……。
右近:「かき混ぜる」ということですか?
坂入:そうです。とにかく常に刺激を作っていかなければいけない。運営は楽になった方がいいと思っていたけれど、演者が自動的に集まるようになってくると、やはりどこかに停滞が生まれてしまいますから。
右近:そのオーケストラはいつまで続けようと思っているのですか?
坂入:みんなで、おじいさん、おばあさんになってもずっと続けようと思っています。
右近:いいですねえ。

坂入健司郎「大阪交響楽団 ブラームス交響曲全曲演奏会」から(Photo: (c)樋川智昭)
ー続ける秘訣(ひけつ)は何でしょう?
坂入:それは自分にあると思うんですよね。毎回新鮮に、新しい曲とか企画を考える。年に2回演奏会をするのですが、自分の半年間の指揮生活の中で、次の曲につながる何かに気付けるよう、自分に宿題を課しています。
例えば、自分の運営するオーケストラでブラームスを演奏する機会がなかったけれど、別のオーケストラでブラームスを振ってみたらすごくいいものが見つかったから、みんなでやってみよう、とか。そんなふうに、各地のオーケストラを振って気付くことは山ほどある。それまでの自分になかったことを見つけて、仲間たちと2、3カ月かけてじっくりトライしてみる、ということを続けています。
右近:自分から選んでやっているというのも大きいですよね。僕にとって、役をもらってお仕事として勤める舞台が自分を育てた家族だとしたら、自主公演は自分が作った、奥さんと子どもがいる自分の家庭という感覚かな。
もちろん、お仕事として役をもらう場合も引き受けた自分に責任はあるけれど、自分からやることにしたものに関しては、そこにかける熱量や焦りがとてつもなく大きい。と同時に、自分がそれを育ててきて、育ててもらってきてもいて、「何があってもこれは僕のものだ!」という安心感もあるんですよね。
ー去年の研の會では、文楽の吉田簑紫郎さんと共演しましたね。
右近:毎年、お客さんに来ていただくことも大変だし、尊いことですが、「やらなくちゃいけないこと」になってくるのは嫌なので、劇場を変えたり今までと違うことを試してみたりしています。2022年に文楽人形に出てもらったのもそれが理由ですし、2020年にはチェロ奏者の内田麒麟さんともご一緒しました。
役者の先輩たちの年表みたいなものを見ると、30代前半はみなさん、実験的なことをなさっている。僕は先人たちがやってきた古典を自分のものにしていく作業が好きですが、自分で新たな舞台を作るという経験もしてみると、ああ、こういうところが楽しいのか、と発見があります。
ー指揮者の方にとっての30代は、どういう位置付けですか?
坂入:僕はサラリーマンをやっていたのでキャリア的には遅いところがありますが、キャリアの多い少ないに関係なく、「30代の指揮者がやらなければいけない仕事」というのはすごく意識しています。
若い頃は小さな編成のオーケストラで指揮者のトーク付きで公演をすることが多いのですが、僕はいきなり1500〜2000人入るホールで大きなコンサートをするようなオファーも頂いたため、若い指揮者が積むキャリアはたしかに少なかった。でも、どちらもすごく大事なことなので、両方やっていきたいですね。
ー一流の指揮者には、音楽性や解釈といった聴覚的な要素だけでなく、視覚面を含めある種の魅力、カリスマ性も感じますが、そのあたりはどう捉えていらっしゃいます?
坂入:僕のスタイルは、カリスマ性より、裸になっても大丈夫なくらい素直になること。例えば音が遅れている時、オーケストラの息のタイミング、弓のタイミングでそうなっているのか、自分の指揮棒のせいで遅れているのかを、瞬時に判断する能力はとっても大切で、それを間違ってはいけません。
だから自分のせいかもしれないと思ったら、まずは素直に「僕、遅かったかな」と聞いてみる。「遅く感じる」と言われたらちょっと速くしてみて、それでスムーズに運べば「僕のせいだ。ごめん、ありがとう」。そういうふうにオーケストラと接すると「この人と一緒に音楽をしていこう」という雰囲気になるんですよね。
ー同世代と音を作ってきたご経験があるから、それができる、と。
坂入:はい。年上年下が関係なくなりました。この前、80歳の方と共演したのですが、何の障壁も感じず、まるでタメ口で話しているかのような音楽のコミュニケーションができて。僕は年をとってもそういう人になりたいと思っています。常に年齢関係なくリスペクトしたいし、それがちゃんと戻ってくる人であれば、どんどん良い雰囲気になるのは間違いない。
そして、丁寧にコミュニケーションを取っていると、本番で「お!」という瞬間があるんですよね。だから等身大で一緒にやって、本番にマジックが起きるといいな、と考えています。実際、それは起きるんです、絶対に。
右近:よく分かります。本当にそうですよね。