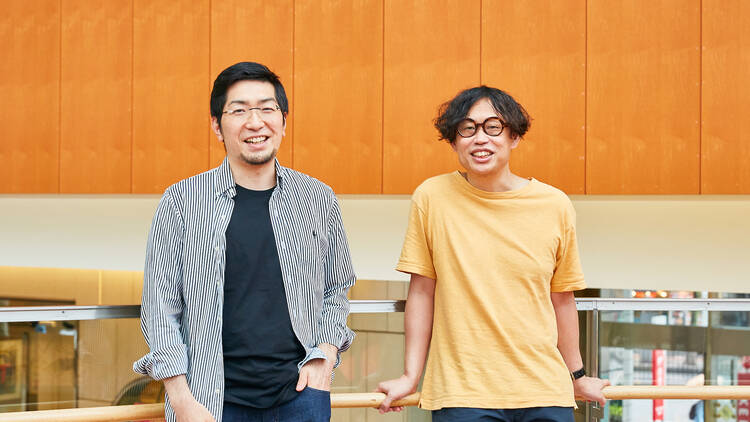オペラにおける「音楽と演技」


―岡田さんは、全国共同制作オペラ 歌劇『夕鶴』で初オペラ演出に挑まれていま
岡田:僕は基本的には、
ところが、オペラではとにかく音楽がとても物語っていて「この音にはこの意味が」みたいなことがすごくある。演劇では主に演者の演技がないとそこに現れないものが、音楽ですでに現れているとしたら、演者はそれやらなくていいんじゃないかと僕は思うわけですよ。同じ情報がなぞられても意味がないから。であれば、どうしたら面白いものになるんだろう、と考えてしまうんです
菅尾:残念ながら僕は『夕鶴』を、観たことは何回かあるけれどきちんと勉強したことないので、自分の中に解釈を特に持たないのですが、作品によって、どちらもあり得るのではないでしょうか。つまり、台本に書いてあ
僕は最終的にはお客さんに物語がちゃんと分かることが重要だと思っていて、そのときに、音楽を皆さんが知っている前提にはしたくないんですね。だから、初めてそのオペラを観る人にどう伝わるかを考えたときに、「この場合はこっちで表現することが必要だな」と思うか、あるいは「これはもう十分表現されてるから舞台上では別のことをやって大丈夫かな」と思うかは、臨機応変と言うか、その音楽をどう感じ
岡田:例えば、ある音形が要所要所で繰り返し出てくる場合、お客さんによって、「あ、また出てきたな」と思える人もいるかもしれないけど、それだけだとそう思えない人もいますよね。そのフレーズが出てきた時、あるビジュアルというか、舞台上で起こっている状況とカップリングされたものが繰り返されれば分かると思うのですが、そういうのはどうしているんですか?
菅尾:絶対逃してほしくない場合は、1回目に出てきた時に印象づけるよう、照明なり演技なりを組み立てれば、次に伝わる可能性が高まるでしょうね。ただ、僕は基本的には、音楽だけが1回出て2回目にまた出た時、
岡田:それは、曲を知っている人前提になるから?
菅尾:はい。そういうのは苦手というか、僕は別のアプローチを選びますね。オペラ作品をよくご存知な上で演出家独自の切り口を楽しみに公演を観に来てくださるお客様はたくさんいらっしゃるし、その期待に応えたいと思う気持ちも少なからずあるけれど、僕は通の人に向かって「こんな意外なことをやりましたよ」とドヤ顔で見せることより、まずは初めて観る人、それこそ子どもでも理解できて楽しめるような舞台を目指しています。ドイツでワーグナーの『神々の黄昏』を演出したときもそうでしたよ。

菅尾友が演出したヴュルツブルク・マインフランケン劇場の『神々の黄昏』 ©Nik Schölzel/Mainfrankentheater Würzburg
『神々の黄昏』は『ニーベルングの指環』四部作の中の4作目ですが、僕が手がけたプロダクションは、全作の連続上演ではなく、『黄昏』5時間半だけの単独上演でした。
『指環』の場合、作品上重要な事物や概念、キャラクターなどを表す「ライトモティーフ」と呼ばれるメロディー的なものが頻繁に出てきますが、全体から独立した舞台では「このメロディーは前作でこういう意味合いで出てきたから、その流れで解釈されるべき」といった文脈的な縛りにとらわれず自由に考えることができて、これがよかった。ワーグナーファンからは「間違いだ」と叱られるかなとも思ったけれど、結果的には好評でした。
逆に、例えば「剣のライトモティーフ」が聴こえる箇所で剣の演技をする、というようにストレートな演出をした箇所もあります。音楽と芝居がハマるという意味では、英雄気分の子役がかっこいいトランペットのメロディーに合わせて高く剣を掲げるのは気持ち良かった。その辺り、演出的なオプションを探る作業が楽しかったし、ワーグナー協会の重鎮が感銘を受けたと言ってくれたのと同時に、この舞台が初めてのオペラ鑑賞だったという少年も楽しんでくれていたのが、とてもうれしかったんです。