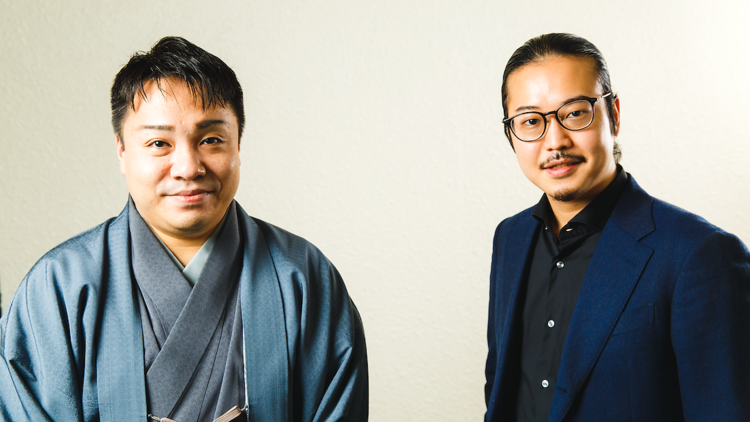新しいボキャブラリーを探す旅の始まり


「文学作品を扱い始めたのは、2008年の年末だったと思います。ローベルト・ムージル『特性のない男』を題材にした『ない男』でした。私自身、それまでは文学作品を踊るということを全然経験したことがありませんでした。演劇とも違いますし、ストーリーを身振りや形で表すということではない。語られていることを直接的に表すだけではない身体のあり方。まったく新しい身体ボキャブラリーを探す、そういう旅の始まりだったのだと感じています」。
20世紀を代表する文学者ムージルに題を採った『ない男』以降、両国のシアターΧ(カイ)では勅使川原による文学作品シリーズが看板の一つとなる。ポーランドの不世出の作家、ブルーノ・シュルツによる短編小説を扱った連作は、ダンスカンパニーと劇場とが長期的な制作に向き合った点で、KARASにとってもシアターΧにとっても重要な作品群だと言えるだろう。とりわけ『肉桂色の店』に着想を得た『シナモン』(2016年初演)は、2019年にも同劇場で再演された人気作だ。
「勅使川原さんは質感という言葉をよく使います。それは意味や感情ではなくて、物でも人でも、色や形、テクスチャ―など何かしらそれ自体が持っている、ほかに置き換えることのできないもの。そういう質感を捉えることを大事にしています。
その点で、シュルツの文体は非常にダンス的だと感じました。言葉が重ねられることによって、書かれていること以上のものが湧き上がってくるように感じられる。特に『肉桂色の店』は、匂いまでも文体から感じ取れるような作品。その意味でシュルツは、作品を読むことも、そのなかに身体を置くことも、とても面白い作家です」。
シュルツは、ガラス板と印画紙を用いた版画作品でも知られているが、その綿密な作業から生み出される幻惑的なイメージは、シュルツ自身の小説とも相通じるところがある。KARASの『シナモン』は、まさにこのシュルツ作品に特徴的な質感を持った空気が劇場に充満していくような、スリリングな舞台に仕上がっていた。言葉を必要としないダンスで小説を表現するということが、説得力とともに示されたと言えよう。一方で、佐東による朗読が重要な要素となる作品も多い。