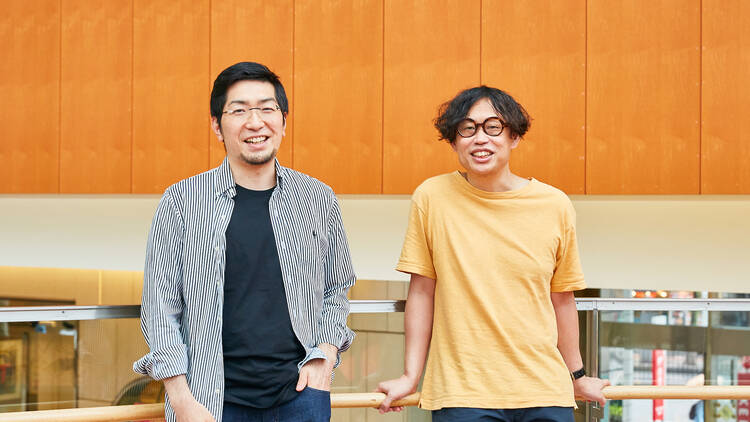言葉と身体の関係を模索して


―今回の公演はどのような経緯でスタートしたのでしょうか?
最初に公演のお話をいただいた時、過去に「JUDAS, CHRIST WITH SOY ユダ、キリスト ウィズ ソイ~太宰治『駈込み訴え』より~」というデュオ作品を一緒に作ったエラ、そして数年前にお会いした中野信子さんと一緒に新作を作ってみたいと思い、お二人にお声がけをしました。
さらに今回は劇場の規模が大きいので、セノグラフィーや衣装などしっかり作り込む必要があると考えて、美術家の川俣正さん、デザイナーの廣川玉枝さん、音楽家の原摩利彦さん、サウンドアーティストの佐久間海土さんといった方々とのコレクティブになったという感じです。
―まず人ありきで、そこからタイトルや具体的なコンセプトを決めていったということですね。
そうですね。踊るという行為って、スタイルが決まっているものでない限り、あるいはパントマイムのように表しているものが明確でない限り、どうしても抽象的になってしまうところがある。だからバレエやストリートダンスは観ても、コンテンポラリーダンスとなると敬遠してしまう人が一定数いますよね。
でも僕は様式や説明より、人との関係や言語によって身体が動かされる感覚に興味を持っています。それは俳優業みたいなことをやっているからというのもあるし、この作品の企画時に注目していたのが舞踏だったということもあります。土方巽さんや大野一雄さんが始めた舞踏には「舞踏譜」があり、膨大な言葉で脳をバグらせる、何かまひさせるところから出てくる身体を志向していたりと、言葉と深く関わっていますから。
そうやって言葉と身体の関係性に興味を持つ中で、脳科学者・認知科学者の信子さんの、身体や表現に対する視座がすごく僕には新鮮で。例えば古典力学などでは、地球はなぜこうなのか、どうしてこの物体はこういう形状で立っているのかといったことを解き明かす。でも量子力学や認知科学になると、ある種スピリチュアルだったり、普段何となく感じていることだったりしたものを言語化しているところがあります。
例えば、信子さんとの会話の中で面白かったのはプラセボ効果。ただのブドウ糖が入っている薬包を、白衣を着た医者っぽい人に「これを飲んだら治りますよ」と渡されて飲むと良くなることがある、とか、逆に「だめだ」と言われ続けたら本当にだめになる、とか。非科学的に見えることを科学的な見地からひもとかれる面白さがある。
科学って、今は宗教に取って代わるほど皆が盲信しているものなので、それでは抽象的な身体の動きを目の前にして、それが科学的な知見で動かされているとなったら人は何をどう見るだろう?と発想したところから、動き出した部分もあります。
―情報があるかないかで効果が違うプラセボと同じように、言葉が身体、そして作品にどう作用するかということを模索するということでしょうか?
出来上がった作品の中に、実際の言葉がどの程度見えるかはまだ分からないのですが、信子さんの言葉なりテキストなりは絶対にあるということから作品が立ち上がっています。
だから、信子さんは出演しないけれど、キャストには、クロスリアリティとしての中野信子ということで「中野信子XR」とクレジットしているんです。リアルとデジタルの境目というか、彼女がいるかいないかは分からないけどでも彼女の名前や写真を置くことで何かしらの想像が生まれてくるんじゃないか。そこからどうパフォーミングアーツ、パフォーマンス公演を見せていけるかな?と考えているところです。