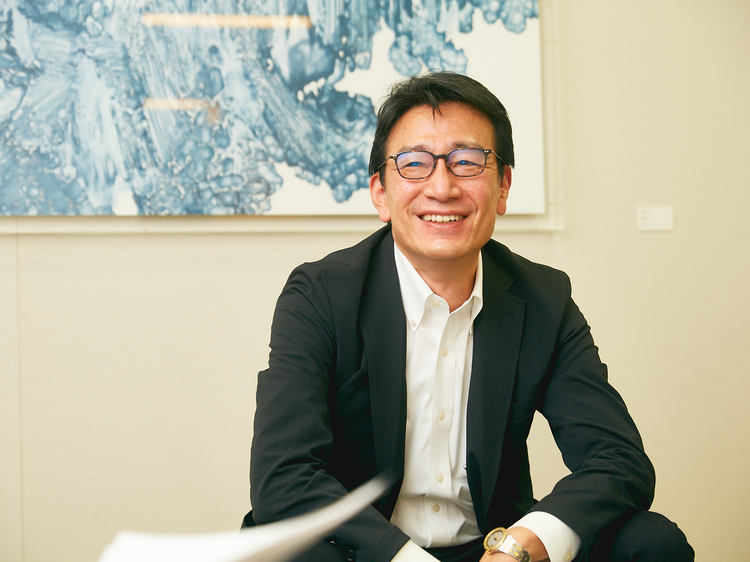―継続性ということで未来の話もすると、釜ヶ崎という街は高齢の男性がとても多い街です。少し嫌な話にはなってしまいますが、この先、数年単位で街が大きく様変わりするのではないかと思います。
そうですね。先ほど釜ヶ崎のためだけにやっているわけではないと言いましたが、今の方が実は街に対して思い入れがあります。釜ヶ崎が薄まっていくというか、上書きされてしまうという不安があるんです。いかんせん地の利がとても良いので、インバウンドの観光客を受け入れるポテンシャルが高いからと、ホテルがどんどん建設されているんですね。泊まってもらうためには安心、安全と、ピカピカのホテル、街もきれいな方がいい。
―1960年代から行政やメディアが「釜ヶ崎」ではなく「あいりん地区」と呼び始めたのもイメージ払拭(ふっしょく)のためだと聞きます。数年前に釜ヶ崎に行ったときにも、すでにドヤではない現代風のホテルがいくつかできていて驚いたことを覚えています。
そうなると、おじさんたちのこととか、釜ヶ崎の歴史とかは「もういい」と、パタンと蓋をされそうな気がしていて、そこに抗いたい。こうした街があったこと、こういう人たちが生きてきたこと、それを後世につないでいく。その役割を担うのは社会学者とか歴史学者とか、研究者たちなのかもしれないけど、ココルームでは表現を扱っている。無名の人たちだけどね、この街で生きてきた一人一人の表現をつなぐことができるんじゃないかと思っています。
―存在した証としての表現。
まだおじさんたち死んでいないので(笑)、アーカイブという言葉を使うことは今はとても違和感があるんですね。私たちはアーカイブのためにやっているわけじゃない。生の存在がちゃんとぶつかり合うというか、そのタネをちゃんと手渡しする出会い方をしたい。いや、ちゃんと手渡せていなくてもいいんです(笑)、出会うということ。それがココルームで一番起こってほしいこと。
―たしかにアーカイブというと死蔵品の匂いというか、古びた印象がありますね。
『さいたま国際芸術祭2020』での釜ヶ崎芸術大学の展覧会タイトルが「ことばのむし干し(星)」としたんです。たくさんの言葉というか作品未満の表現がたくさん集まっているんですが、やっぱり時々は虫干ししないと、風を通さないとだめよね。そのことによってまた誰かに出会ってもらう機会にもなるので、そういう仕組みというか仕掛けを作るのは、表現を取り扱う者が担っている役割だなと感じています。
―「言葉の虫干し」というのはとても面白い言葉ですね。虫干しって長く使うためにする行為ですもんね。本でも着物でも、それこそ何世代でも受け継いで使っていくための。
つないでいくこと、多くの人たちに出会ってもらうこと、その気持は数年前よりもだいぶ切実になってきています。なぜそんなにこだわっているかというと、これまでにおじさんたちの看取(みと)りというか、死に際に何度か立ち会ってきたからなんです。死ぬ前の数カ月、とんでもない優しさで私たち若者に接してくれるんですよね。家族に捨てられたか、捨てたか、たった一人で生きるおじさんたちが、死ぬ間際に手渡してくれたものの大きさ。この尊さを受け取った者として、このタネをいろんな人に手渡したい、出会ってもらいたい。
―2016年からはゲストハウスとしても運営されていますが、これも「出会い方」に大きな変化を及ぼしていそうですね。
今はコロナで来られませんが、外国の人たちもたくさん来てくれてリピーターも多いです。釜ヶ崎の歴史に興味を示さない人もいるし、おじさんたちに話しかけられて逃げていくような人もいるんだけど、なかにはココルームの活動に関心を持って参加してくれたり、おじさんたちに興味を示して長期滞在を始めたりした人もいます。長期滞在の外国人とおじさんがすごく仲良くなって、毎日いつもハイタッチしていたの。ほかの釜ヶ崎のホテルでは、旅人と地域の人とが出会うようなことはないので、交流したい人にとっては面白い宿だと思います。
―それこそ釜ヶ崎芸術大学に参加して、地域の人と一緒に書道したりというのも旅の思い出としてとても印象深いものになりますよね。旅慣れている人ほど、街の本当の顔というか、ローカルな体験を重視すると思うので、海外からのリピーターが多いというのもうなずけます。これだけ「出会うこと」を大事にしているココルームなので、コロナ禍の影響も非常に大きかったと想像します。先ほど、一日も閉めていないというお話もありましたが、リモートに活動を移行するのも難しかったのでしょうね。
でも、釜ヶ崎のおじさんたちのことを気にかけてくれている外の人たちもいるので、コロナで移動できなくなったときに、釜ヶ崎芸術大学はリモートとのハイブリッドにしましょうと、2020年3月には決めていました。Wi-Fi環境にない釜ヶ崎のおじさんたちにはここに集まってもらい、先生やほかの参加者はオンラインという形で開講したんですが、もともと関係ができていたこともあって、空気感はそのまま、熱量もそんなに変わらず。おじさんたちも画面に向かって「先生ー」って手を振って(笑)。
―オンラインのいいところも使いつつという感じですね。コロナに関する助成金についてはいかがでしたか?
大阪の芸術のための助成金についてはココルームには向いていなかったですね。オンライン配信などに対するものが主だったんですが、大規模な配信を行う気はなかったので申請はしなかったです。もうちょっときめ細かな助成金があるといいなと思いました。その点、京都市がいち早く実態調査をしているのは大したものだと思いました。それはこれまでの積み重ねですよね。困っている人の顔が見えているというか。
―支援する側と支援される側のコミュニケーションが厚かったということでしょうか?
そうですね、公益財団法人が運営している京都芸術センターは、地域の表現者にとってのアトリエや稽古場として日々運用されていますし、小さな発表会にも関わってらっしゃいます。さまざまなジャンルの人たちが交流しやすい雰囲気もあるし、その実績がありますよね。舞台芸術祭の『Kyoto Experiment』や『KYOTOGRAPHIE』など、ネットワークしてきた取り組みの多さもあり、これまでの積み重ねのおかげだろうと思います。
―具体的にどういう支援の制度があったらいいというよりは、どういう団体が今どういう活動をしているかとか、こういう特性の団体だからこういうことに困りそうとか、そういう情報を日々集めていくことが大事なんですね。それが、コロナ禍のようなこれまでに経験のない事態での支援にも功を奏したと。上田さんご自身も、2021年度から大阪府堺市のアーツカウンシルのプログラムディレクター(PD)に就任され、支援する側にもなりますよね。
びっくりですよ(笑)。これも公募じゃないんですよ。随意契約で声をかけられて。堺市さんは、芸術については社会包摂にかじを切っていきたいという方向性を打ち出していて、それで1年前から芸術振興会議の外部委員として私も入ることになったんですね。会議に出て、さまざまな団体のヒアリングにも出席するなかで、堺市さんから「アーツカウンシルを立ち上げるからPDになってほしい」という打診がありました。
―堺市には、障害のある方による舞台芸術の制作にも力を入れているビッグ・アイさんなどもいて、上田さんが堺アーツカウンシルに入ることでまた良い出会いがありそうだと期待しています。
本当にそうありたいと思います。ビッグ・アイさんにはこの間も伺ってお話を聞いてきたところです。私自身は堺市のことはあまり知らないし、ココルームの活動も大変だし、PDの話はどうしようかと思っていたんです。でも、ココルームの活動も20年近くなり、ここ数年は大阪府豊中市さんや奈良市さんの委員もさせてもらっているんですが、そうした審議会にいらっしゃるのはやっぱり大学の先生とか、有名なキュレーターの方とか。そういうなかで、現場ではいつくばっている人間が発言するというのは大事だと思い、お受けしました。それを、現場の人間を一応呼んでいるだけ、という風に使われたらもっとあかんのですけどね(笑)。