[title]
現在の世界的な危機のなか、多くの都市のクラブ、ライブハウス、レコード店が営業休止を余儀なくされている。しかし、音楽の世界を広げる方法は、まだいくつもあるのだ。ここでは、音楽にまつわる最高のドキュメンタリー作品を紹介したい。全て無料で視聴できるものばかりなので(Netflixなど「いつものサービス」は、一旦忘れて)、ぜひ楽しんでほしい。

『LDN』 (Nathan Miller, 2017)
ロンドンにおける現代のグライム、ドリル、ヒップホップの広がりを決定的に捉えたドキュメンタリー。誤解されがちでもあるこれらのシーンだが、その熱量や盛り上がりをリアルに感じることができる。登場するのは、J Hus、Kojey Radical、67、Fredoなど。監督はドキュメンタリー映画作家、ネイサン・ミラー。彼はロンドンのエースホテルでアルバイトをしながら、この作品を作り上げた。

『The Burger and the King』 (BBC, 1995)
「エルビス・プレスリーと食べ物」との素晴らしく、少し不思議な関係性を伝えるドキュメンタリー。食べ物をこんなにも愛していた彼だからこそ、一生のうちにフライドピーナッツバターサンドをあんなに食べていたのだ、と納得させられる。
The Sound of Belgium (Director's cut) from Jozef Devillé on Vimeo.
『The Sound of Belgium』 (Visualantics, 2018)
伝統的なオルガン音楽からテクノ音楽へと時代を進めながら、ベルギーのダンスミュージック界の歴史に余すところなく迫り、紹介するドキュメンタリー。2020年4月5日(日)まで、ディレクターズカット版が無料で楽しめる。
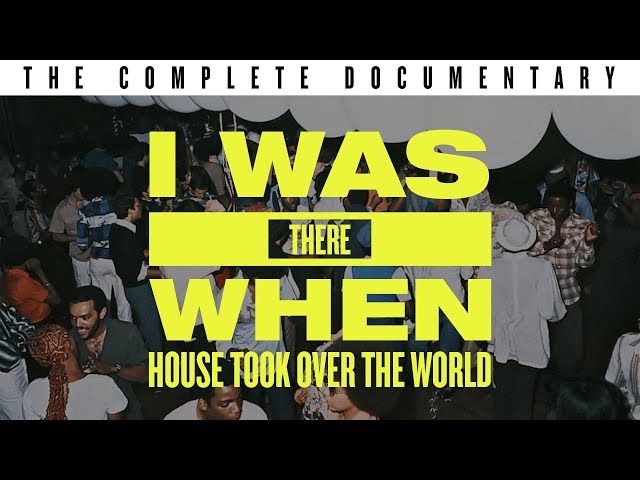
『I Was There When House Took Over the World』 (Channel 4, 2017)
ハウスミュージックの誕生をテーマにしたドキュメンタリー。2部構成となり、前半ではシカゴのシーンの始まり、後半では、世界での広がりにスポットを当てている。ナイル・ロジャース、マーシャル・ジェファーソン、ハニー・ディジョンなど、シーンの中心にいた人物から若手DJなどへのインタビューもたっぷり。

『Marc Bolan – The Final Word』 (BBC, 2007)
T・レックスの音楽は、滑らかでクールなギターフレーズにあふれていた。BBCが制作したマーク・ボランの幼少期、名声、悲劇を描いたこのドキュメンタリーで、その魅力を改めて感じてみよう。1970年代の究極のミューズの姿も見ることができる。ナレーションを担当しているのはスージー・クアトロだ。

『Fantastic Man: A Film About William Onyeabor』 (Alldayeveryday, 2014)
ナイジェリアのファンクアーティスト、ウィリアム・オニーバーについてのドキュメンタリー。監督のジェーク・サムナーは、デイモン・アルバーンやカリブー、フェミ・クティなどと語り合い、ナイジェリアを旅してこの作品を完成させた。魅力的で美しい光景を見ていると、自然にファンクの魔術師の物語に引き込まれるはずだ。

『Chas and Dave: Last Orders』 (BBC, 2012)
愛すべき悪ガキ二人組、クリスとデイブは、「ロックニー」と呼ばれる音楽スタイルを確立したことで知られる。ロックニーは、ロンドンのパブロックと古き良き時代の音楽を演芸風にブレンドし誕生した音楽だ。ドキュメンタリーでは、二人の50年間を振り返り、人々を笑わせ続けてきた歴史の背景には「本物の音楽」があったことを伝えている。

『The Story of Funk: One Nation Under a Groove’』(BBC, 2014)
「ファンクはセンセーション。つまり、別の次元の普遍的な感覚ようなもの」。ファンクへの探求である本作は、このフレーズで始まる。ジェームス・ブラウン、スライ&ザ・ファミリー・ストーンのアーカイブ映像がたくさん使われている、文字通りファンキーな作品だ。
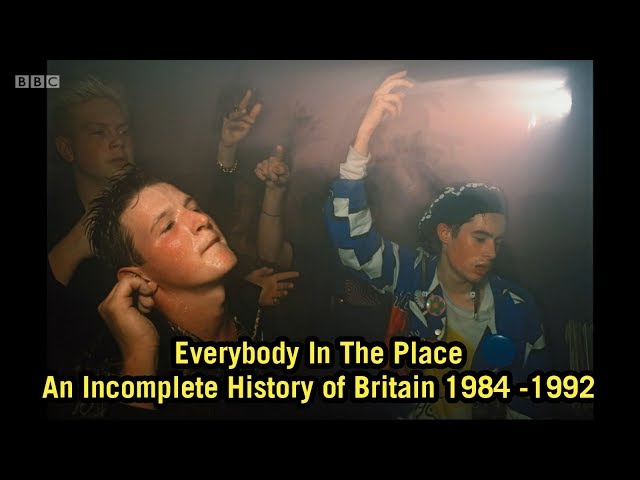
『Everybody in the Place: An Incomplete History of Britain, 1984-1992』 (BBC, 2018)
やや重苦しいタイトルではあるが、作品には新しさを感じることができる。ターナー賞を受賞者であるアーティストのジェレミー・デラーは、表現の場を学校の教室に移し、レクチャー形式で生徒たちにアシッドハウスの歴史を伝えている。ハウスミュージックファンだけでなく、全ての音楽好きにおすすめの作品だ。

『The South Bank Show: Talking Heads'』(LWT, 1979)
イギリスのドキュメンタリー番組、サウスバンクショーで収録されたトーキング・ヘッズ特集。『フィア・オブ・ミュージック』の頃の、非常にシャイなデヴィッド・バーンらの姿が見られる。
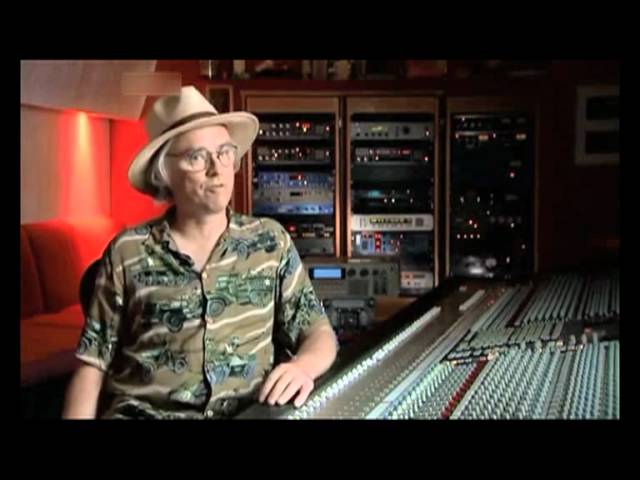
『Classic Albums: Screamadelica』 (BBC4, 2008)
プラマルスクリームの衝撃作『スクリーマデリカ』の制作過程に迫ったドキュメンタリー。アルバムのコンセプトについて惜しみなく語るバンドメンバーの姿が詰め込まれている。また、故アンドリュー・ウェザオールの美しく、痛烈で辛辣(しんらつ)な言葉も随所に。
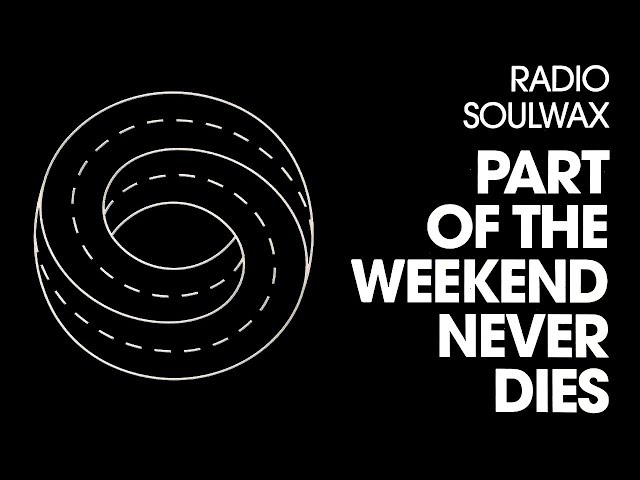
『Soulwax: Part of the Weekend Never Dies』(Partizan Films, 2008)
1台の手持ちカメラで撮られたSoulwaxのツアーと、それにまつわる出来事を捉えたドキュメンタリー。2 Many DJ'sとしても活動し、2000年初頭に大爆発した彼らの人気ぶりを目の当たりにする絶好の機会になるだろう。

『Showdown at Glastonbury』(Channel 4, 1992)
フェス好きは絶対に見るべき作品。1992年に、グラストンベリーフェスの会場となっていたマイケル・イービスの農場の反対側に住むキリスト教原理主義者が、フェスに反対してメインステージの向かいに巨大な十字架を設置した。
ネタバレ注意:そのキリスト教原理主義者は、結局フェスを閉鎖できなかった。イギリスのフェスシーンに反旗を翻した人も存在した時代を思い出させる作品だ。
関連記事『イベント自粛の裏で、PAエンジニアたちの苦闘』
