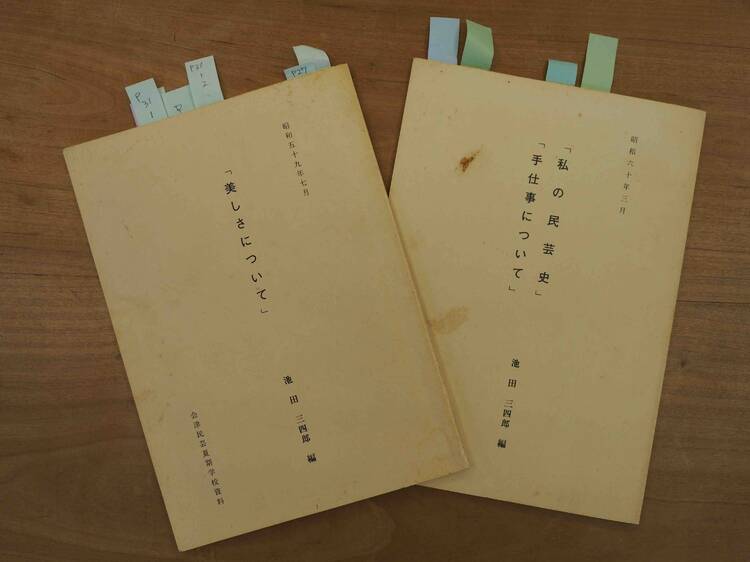カップルがデートに訪れる福祉施設


敷地内にはここで暮らす障がい者の居住棟のほか、施設の利用者が布や土、紙、木などを使って思い思いに手を動かす4つの工房、ギャラリー、オリジナルグッズのショップ、ベーカリー、そば屋(現在休業中)、イタリアンのレストラン、少し離れた場所には250席のキャパシティーを持つホールもある。
工房の見学には事前の申し込みが必要だが、一般の人も園内で飲食をしたり、ショップで買い物をしたり、ロバとヤギがいる芝生の中庭でくつろいだりするのは自由。ホールでは、アーティストの公演が開催されている。
全国的にも珍しい、地域に開かれたこの知的障がい者支援施設の特筆すべき点は、周囲に観光名所があるわけではないこと。来館した1万人にとって、しょうぶ学園は「目的地」なのだ。
両親が開いたこの施設で、前例のないアイデアを次々と実現してきた福森は、「僕にとっては奇跡です」と目を細める。
「ここには、若いカップルもよく来るんですよ。デートっていいところに連れて行こうと思うじゃないですか。そういう場所に選ばれるって、うれしいですよね。中には、結婚式で使う写真を撮りに来る人もいます。障がい者の支援施設として、これだけの人が訪ねてくるところは世界的にも珍しいんじゃないかな」