[title]
オリジナルのパズルやボードゲームで遊べる店「発明家ショップトキメキ」に行ってきた。浅草駅から徒歩3分、スカイツリーのお膝元にあるソレは、外観の時点で既に只事ではないオーラをビンビンに放ちまくっていたが、取材班を快く出迎えてくれた発明家オーナー・関場純もやはり只者ではなかった。

一見、気さくなおじさんという感じだが、澄み切った目から放たれる眼光は鋭い。そして機関銃のようにしゃべり続ける。その大半は自慢話以外の何物でもなかったが、不思議とイヤな感じはしなかった。野球少年が自分の活躍ぶりを親に語って聞かせるような、ほほえましいイノセントさがある。純真で明晰な変わり者。スラングでいうなら「早い」し、「パキパキ」。まさに発明家という感じだ。
面白すぎるバイオグラフィー
関場が発明家として開眼したのは、中学校発明コンクール。全国の中学生が発明品を競うというこのコンクールで関場は変形傘を作って入賞したのだという。審査員の「この子には人と違う発想がある」という言葉に舞い上がった関場は、発明を自身のライフワークに定める。
そして大阪万博のころ、大学を卒業した関場は、大阪の製造会社に就職。ケガが起きない工場にしたい、という思いから関場は次々にアイディアを連投、その斬新な視点が評価され開発部に異動となる。

ここまではいかにもありそうな話だが、ここからが凄い。その開発部で、なんと関場は「初心者マークのマグネットシート」を作ったという。当時は鉄製のものをボルトで締め付けて装着していたそうだが、より安全で簡易的なものを、ということで制作。そうして苦心の果てに開発されたマグネットシートだったが、警察は「こんなの風で飛ぶんじゃないの?」となかなか許可を出してくれない。

そこで関場は一計を案じた。東京・名古屋間を走る新幹線に勝手にマグネットシートを貼り、ゲリラ実験を行ったのである。結果、新幹線のスピードでも剥がれないことが判明し、見事に許可を取り付けたという。
彼の半生は、こういう「ほんとかよ」というようなエピソードの宝庫だ。三億円事件の容疑者として取り調べを受けたとか、保険レディーをやっていた妻が新興宗教に入信してしまったために離婚したとか、ドクター中松に表彰を受けてメダルを貰ったとか(マジで滅茶苦茶格好良いメダルだった)、若かりし頃の爆笑問題の番組に出たとか、加山雄三の番組に出たとか、強烈な話が次から次へと出てくる。ここで紹介しきれないのが残念だ。

その語り口はおもしろく、何より地頭の良さを感じさせる。聞けば教員免許も宅建も取得しており、シンプルにめちゃくちゃ優秀な人なのだと思う。現在77歳だというが、まったく老いを感じさせない。バイタリティーも頭の回転もすさまじい。
ヒラメキ工房の誕生
転機は50代に訪れた。東京のおもちゃ会社から「関場が考案したゲームを出したい」というオファーが来たのである。だがなかなか関場の発明品を世に出してくれないどころか、給料が毎年下がっていくという低待遇に業を煮やした関場はついに独立。発明家仲間とともにNPO法人・ヒラメキ工房を立ち上げ、「発明家ショップ トキメキ」をオープン。

当初は両国に店舗を構えていたが、民主党政権時代に事業支援を受けて現在の場所に居を移し、発明家仲間の商品なども扱いつつ、自作のパズルやボードゲームを販売しているということだった。ちなみにヒラメキ工房は公式テーマソングが存在しているが、この作詞と振り付けも関場によるもの。これもマジでヤバいので、読者諸君は是非YouTubeでチェックされたし。
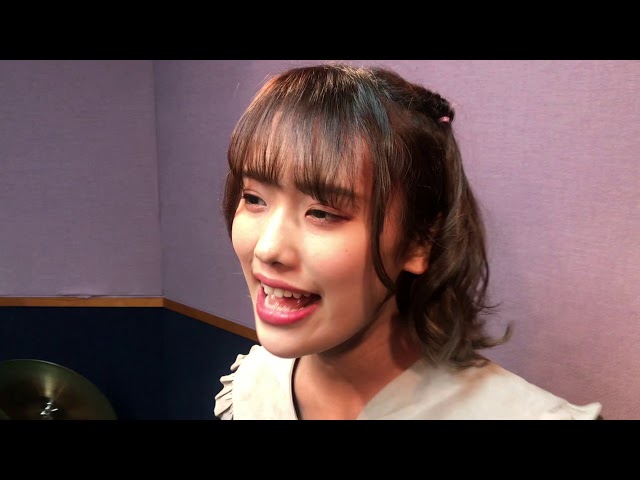
脳ミソが発熱するパズル
で、波瀾万丈な関場の半生をたっぷり聞いた後、ついにゲームを紹介してもらう。最初に出てきたのは新作パズル「ブルースター」。
白とピンクとブルーで出来た多面体の厚紙を、折り紙の要領で折って一色の花を作るというものだが、これがなかなか難しい。関場は毎週小学校の教壇に立ち、自作ゲームを子どもたちにレクチャーしているそうで、「つーことは子ども向けっしょ? 楽勝だろ」とタカをくくっていたが、予想を遥かに上回る難度だ。同行したカメラマンと二人で悪戦苦闘しながら何とかブルーの花を作り上げることに成功した。

前述した通り関場は早いので、達成の喜びに浸る間もなくさらなる一手を繰り出してくる。次に出てきたのは通算5000枚を売り上げたというベストセラー「キラメキ」だ。三角形折りたたみ教育的パズルと題されたソレは、5色(赤・青・黄・緑・黒)からなる三角形のプラスチックシートを折って、指定の組み合わせで図形を構築するというもの。

簡単に言うと、折り紙とルービックキューブのミックスなのだが、これが面白い。難易度は「園児」クラスから「天才」クラスまで14段階あるが、「小1」の時点でもう結構難しい。脳味噌の普段まったく使われていない箇所が発熱するのが解る。われわれが苦心しながらパズルを解いている最中、関場は嬉々とした顔で「小1だよ! 小1の子はみんな出来るんだよ!」とひたすら茶々を入れてくる。少年的なサディスト傾向を感じるが、やはりギリギリのところでイヤではない。本当にチャーミングな人間だと思う。
オセロと将棋の欠点とは
そうして「小4」をクリアした辺りでギプアップした我々に提示されたのは「反転はさみゲーム 遊宝」だった。オセロに似ているが、フィールドが円環状になっている。我々が頭上にでっかいクエスチョンマークを浮かべていると、関場が問いかけた。
「オセロの欠点って何だと思う?」
「えーっと……8×8で偶数だから、引き分けが存在すること?」
「そう! だから私はその欠点を克服するゲームを作ったの。引き分けだからジャンケンで決めるなんていうとさぁ、子どもは絶対納得しないからね」

百聞は一見に如かず、ここからは関場相手にプレイ。前後を挟めばひっくり返るという基本ルールはオセロと同じだが、それが円環状になっているというだけで、ぐっとゲーム性が変わってくる。オセロとはまるでセオリーが異なる。至ってシンプルなはずなのに、体感がまったく新しい。正直言ってすげえ面白い。もはや書くまでもないと思うが、このゲームの間も関場はずっとしゃべり続けていた。その次に登場したのは、ベクトル将棋&グーチョキパーゲーム。

「将棋の欠点って何だと思う?」
「えーっと……経験者が圧倒的に有利で、ルールが複雑なこと?」
「そう! だから私はその欠点を克服するゲームを作ったの。駒の動きが矢印で書かれてるから誰でもわかるし、子どもでも大人に勝っちゃえるの」

これもシンプルなようでいて、物凄く良く考えられている。基本ルールはほぼ将棋と同じだが、飛車や香車のように一気に進む駒が存在せず、1マスしか進めない。そして最初の配置はプレイヤーの自由で、どこに何を置いても良い。それだけでやはり、ゲーム性が大きく変わる。フォーマットとしては馴染みのあるものなのに、手触りが新感覚。それでいて盤面のコマ数が小さく、1ゲームが五分あたりで終了するコンパクトさも良い。駒を裏返すと別種のゲーム・グーチョキパーゲームが遊べる。
これも基本ルールは将棋と同じだが、ジャンケンで勝てるコマしか取れないというルールがおもしろく、非常に良く出来ている。
生きていく上で大切なこと
その後も点字をなぞりながら国旗を当てるユニバーサルデザインの絵本や、関場が小学校のときに考案したという「計算トランプ」などなど、ひたすらゲーム三昧。関場は「まだ時間あるかな? 次はこれちょっとやってみよう!」と、次から次へとゲームを繰り出してくる。本当に屈託のない人だと思う。関場のマシンガントークとゲームデザインの巧妙さに魅入られて、気がつくと3時間半が経過していた。脳ミソはヘトヘトに疲れ果てていたけれど、肉体労働のあとのような、快い疲れだった。

ゲームは子ども向けだが、まったく子ども騙しではない。むちゃくちゃ誠実に向き合っている。関場はゲームを通して、子どもの自尊心を高めたり、コミュニケーションの場を作ろうと切に思っている。彼の手がけるゲームには、どれもその真摯な態度と着眼点のおもしろさが光っている。
最後に店名の由来を聞くと関場は「人間が生きていく上で大切なのって、いろんなことにときめいてドキドキすることじゃない! ヒラメキ、キラメキ、トキメキ!」と言った。マジで同意。僕は関場を完全に支持する。
関連記事
『スタジオジブリ幻の名作『海がきこえる』が3週間限定の全国リバイバル上映を開催』
『石野卓球の年末恒例パーティー「地獄温泉」の歴史をたどるイベントがKATAで開催』
東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら

