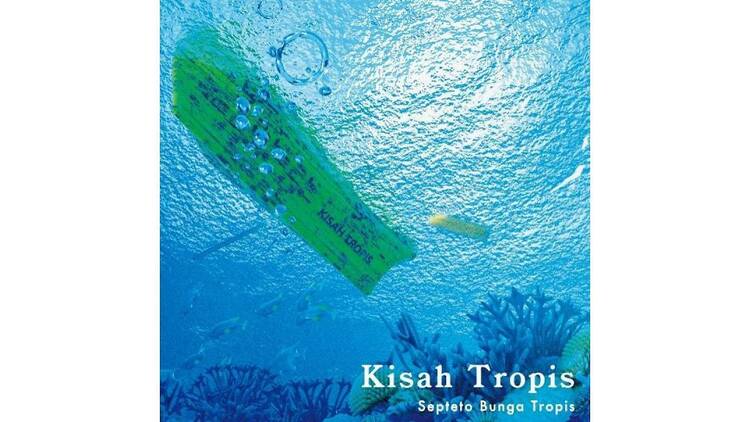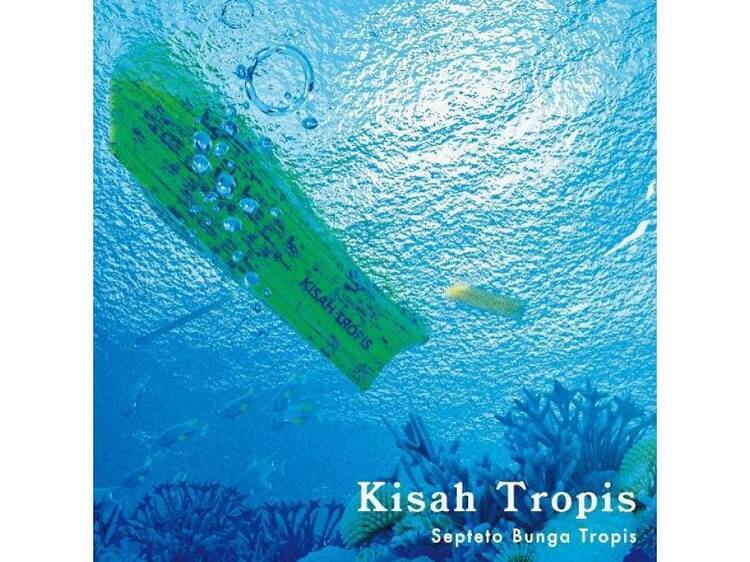タイムアウト東京 > アート&カルチャー > 普遍の熱帯音楽、Septeto Bunga Tropisの髙井汐人にインタビュー
菊地成孔が率いていたDC/PRGの元メンバー・髙井汐人。2010年の再結成時以来、活動終了までテナーとソプラノサックスを務め続けた男である。菊地をして「天才」と言わしめた彼が主催する7人組のラテングループ・Septeto Bunga Tropisが先日、5年ぶりの新作となるセカンドアルバム『Kisah Tropis』を発売した。
熱帯における大海原や街の喧騒(けんそう)をイメージしつつ、中南米のグルーヴに限らない、まさにタイトルである「熱帯のストーリー」を表現した作品である。メンバーには中嶋錠二(ピアノ)、ヤマトヤスオ(ベース)、田中教順(ドラムス)、池宮ユンタ(パーカッション)といった髙井と同世代の面々に加え、中路英明(トロンボーン)と大儀見元(パーカッション)という大ベテランまで参加する。
しかし、演奏スキルの高さと裏腹にメディアへの露出は少ない。音楽以外のことに興味が薄いのかもしれないが、もっとフォーカスされるべき存在であるはずだ。そんな気概を持って、新作のリリースライブを2024年8月27日(火)に控えるSepteto Bunga Tropis・髙井の初インタビューを届けよう。
大自然から大都会まで、音が物語る熱帯の情景
Photo: Septeto Bunga Tropis ー『Kisah Tropis』というタイトルについて教えてください。
髙井: 「熱帯のストーリー」みたいな意味です。各曲も熱帯の大自然から大都会まで、いろいろなシーンにちなんだ情景を思い描けるような、情景描写的なタイトルを付けていきました。
とはいえ、特定のイメージはありません。例えば熱帯の暑かったり雑然とした感じ、あるいは自然があふれる感じなどのイメージを膨らませたり、誰かの思い出話を聞いてるように楽しんでもらえたらうれしいです。実際、自分もこれまで経験した情景から着想を得た曲もあるので。
ートロンボーンのテーマから始まる「Pantai Kosong(誰もいないタッチビ)」という曲が印象に残りました。この曲にも背景となる情景がありますか?
突然「伝統的なボレロと、ポップスっぽいリズムが同居した曲を作りたい」とひらめいて、こうなりました。与論島の車1台がギリギリ通れるとは言い切れないぐらいの農道みたいな道に入って、茂みをかき分けていくと横に長い大きな浜があるんですよ。しかも誰もいないんです。そこへ、親戚のおじいちゃんが連れていってくれた思い出。その場所がタイトルになりました。
今でも1人で行くんですけど、ほとんど誰にも会いません。そんな場所で何というか……人間のことを考えなくなるっていうか(笑)。自分と自然しかない貴重な時間です。多分おじいちゃんやほかに訪れた先人たちも、同じような気持ちだったんだろうなと。そんな思い出話をトロンボーンのメロディが語っているようなイメージが湧いたんです。
ーラテンミュージックというと中南米ですが、日本を連想しても問題はありませんか?
私もスペイン語圏ではなく、東南アジアで育ちました。でも、私たちの演奏はサルサやキューバ音楽で使われる語法を忠実に使いつつ、それ以外の西アフリカのリズムを使ったりもしているので、汎熱帯でパントロピカルなイメージを喚起できるとは思っています。
ーそのほかにコンセプトなどは?
新しいことを試しながらも、奇をてらった感じにはしたくなかったですね。あたかも元からどこかの土地に古くからあったかのような、時代性を帯びていない音楽にまとめていきました。多分、このアルバムって10年前に出しても、10年後に出しても印象が変わらないと思うんですよ。だから、最近の音楽的な文脈や構造はあえて意識していません。
ーちまたで人気だったり、SNSでバズっている現代ジャズやサルサとは無縁だということですね。
そういったことは「やりたければやる」というだけですね。方向性といえば、今作だと「ゆっくりな曲を作ろう」といったシンプルなテーマが曲ごとにあるくらい。
自分のルーツである与論島で、サルサがかかっていたわけではないんですよ。でもその風景と自分の作ってる音楽は合うとは思っています。ジャカルタの喧騒だろうが、マレーシアに住んだ時の雑然とした雰囲気にも合うはず。
ーアレンジは毎回、どういうふうにバンドで決めていくんですか?
基本的な構成は私が最初から作ってリハーサルに臨みます。それ以外の、リズムトリックをメンバーの誰かが提案してくれるとか、ベースがどこから入るとか入らないとか、そういうのは各員の裁量に任せています。
演奏の仕方は作曲段階でイメージした範囲のこと、楽譜に書くくらいのことは言いますが、それ以上のことは何も言わないですね。皆が自由に演奏する中で、作曲前の想像を超えていく感じ。
唯一無二の柔らかく伸びやかなサックス
ー髙井さんの演奏スタイルは、どういうところから影響を受けているのでしょう?
ラテンにおけるサックスって、ソロを多く吹くポジションではないんですよ。だから参考にできる奏者の数も少ないし、あとは活躍してる人の音もチャーリー・パーカーの音を硬くしたみたいなギラギラした音の人が多い印象。自分のような柔らかめで、ハードバップ以前のジャズみたいな音色のプレーヤーっていないんです。
だから、ラテンサックスの誰かを参考にしたことはありません。ロングトーンが多めなのも、シンガーの人がバラードで音を伸ばすのと同じ感覚でやっている気がします。思慮深げに吹くか盛り上げる以外の場面で、サックスが朗々とロングトーンを使って歌う場面は意外と少なくて。ほかには、ピアニストやパーカッショニストのプレイが参考になっている部分もあると思います。
いかにもサックスらしいジャズの語法も、身に付いたのは1950~60年代ぐらいまでのテクニックかなと思います。モードジャズ以降の何かを追いかけたことはないですね。後期コルトレーンも好きじゃない。結局、私は気分でしか音楽を聴いていないし、吹きたいものしか吹いていないんですよ。
菊地成孔から受けた影響、過去には「そっくり過ぎる」とも
Photo: Keisuke Tanigawa ー髙井さんは菊地成孔さんのグループ・DC/PRGに参加し、演奏されていましたね。自身が受けた菊地さんからの影響って、現在はどういうところにあると思いますか?
新作に収録した『¡Bunga Pop!』などリズムトリックが多い曲があったり、3:4のポリリズムをいつでも往復できたり、そういう世界があると啓発してくれたのが、菊地さんと池宮ユンタさんですね。それは非常に大きい。あとサックスのスキルで言うと、菊地さんの突然出てくるパーカッションっぽい、不思議なリズムのフレーズの感じは、今も自分の特徴として残っています。
一時期は、菊地さんのビブラートのかけ方や節回しを「完コピ」するぐらい真似していたんですよ。でもDC/PRGに加入したばかりの頃に、メンバーの津上研太さんから「自分のアイドルみたいに吹けるのは楽しいかもしれないけど、菊地さんにそっくり過ぎる」と言われたことがあって。
津上研太からもらった忘れられない言葉
ーほかに、DC/PRG時代の印象的なエピソードなどがあれば知りたいです。
打ち上げの時に揚げチーズ餅を指して、研太さんが話してくれた内容も記憶に残っています。「これを美しいと思ったとしたら、それを音に乗せて伝えるのが俺らの仕事。そのために音楽の神様から俺らは演奏する能力をもらって、それでそのステージからお客さんに届ける。そうしたら音楽はまた神様のところに還って、再び俺らに回ってくる」と。
抽象的ですが、シーンや新しい文化が生まれるとか、文化が受け継がれていくと捉えたら納得しやすい。それでいて音楽は原始的なものなので、神様というか人知を超えた存在を想定して説明してくれたんですね。自分のアイドルそっくりに吹くだけではなく「美を伝える自分の方法を見つけろよ」ってことだったんじゃないかな。恐らく本人は覚えてないと思います(笑)。
ーなるほど。話を新譜に戻すと、『Hotel Excelsior 815』は古き良きハードバップぽさも感じさせる楽曲ですね。
最初は曲が似ているので「ケニー・ドーハム」と呼んでました。対旋律で動くところをハードバップっぽく作りたくて、後半はモントゥーノのブレイクからサルサで盛り上がっていきます。タイトルは、幼少期にマレーシアへ移住して、家も決まっていない時に1カ月くらいステイしたホテルの部屋。
渋滞や天候が突然変化したり、マレー系、中国系、インド系の文化・宗教が共存していたり、混沌(こんとん)としているんですね。その慌ただしい、特殊な秩序を持っている感じを曲にしました。私にとっての熱帯の原風景ですね。
東京が持つ可能性と良い雑然
Photo: Keisuke Tanigawa ー熱帯で育った髙井さんは、東京という街をどう見ていますか。
スピリットとして、東京全体をホームタウンとして感じることはないですね。幼少期に少し住んでいた足立区に思い入れがあるくらい。自分にとっての東京の意味は、人脈や環境の部分が大きいと思います。可能性が無限に広がっていく感じ。
それを感じたのが、DC/PRGに参加した時なんですよ。ヨスバニー・テリー(サックス)やリッチー・フローレス(パーカッション)は来るわ、JUDY AND MARYのTAKUYAと共演できるわ……。
みんな、東京でなければ会えなかったはずの人たち。もし私がニューヨークに渡っていたら、違う結果だったと思うんですね。プエルトリカンの人たちがサルサをやっていたり、ジャズの学校があったりとか。私は「特定のジャンルの本場で学ぶ」という音楽のやり方ではなかったので、今こうして混じり気のあるバンドをやってるのかなと。それもこれも、東京だからこそできたこと。
ーなるほど。
例えば普段、日常の食材を買いに行くのは上野にある「アメ横センタービル」の地下なんです。あのアジアっぽい雑然とした空間を東京の中で嗅ぎ付けて、自分の生活空間の一部にしているのかもしれません。あとは、東京の誰かに自分の持ってる熱帯性のある音楽だったり、料理だったりを発信できるのもいい。
ここ10年ぐらいで日本人の舌に合わせていない、ガチなインド料理屋さんが増えたと思うんですよ。そこに興味を持つのが、インド人とインドに住んだ経験のある人だけではなくなっている。インドのことは全く知らないけど、鬼のように詳しい人がいっぱいいるんですよね。特定の文化や国にひもづいたものが、全然違うコミュニティーにいる人に届く可能性は、ほかの街や国だともっと低いんじゃないかな。
インスピレーションの源にある上質な楽器たち
ーそれから髙井さんは、サックスを多数所有されているとか。その理由は?
数えてないので総本数は覚えていませんが、「この曲をこのバンドで今日やるから」という感じで吹き分けてますね。聴く側は分からないと思うんですけど、やっぱり演奏する時のアイデアが違う。
出てくる音楽が変わるので、そういう感性を得られる楽器ばかりを買っていますね。自分がやりたいことを表現できる道具としてではなく、触って吹くことによって新しい音楽を思い浮かぶような。ほかには、彫刻も含めてクラフトマンシップがすごいですからね。
人間の細かい思考の及びもしない、根源的な美に対する欲求は言葉にも音にも仕切ることはできませんが、抽象的なインスピレーションは大事にしています。それをもとに音楽をやりたいし、道具も選んでいきたいですね。
ー8月のリリースライブでは、どの楽器を吹きますか?
録音の時に使った1939年製造のアメリカンセルマー社・バランスドアクションか、 1953年製造のセルマー社・スーパーバランスドアクションのどちらかですね。どちらも小回りがきく、繊細でシャープな感じ。小さい音から大きな音までいろいろな気分で吹きたいから、そういう柔軟性のある楽器がいいなと思って。まあ、今から間違って新しい楽器を買ったりしなければ、の話ですけど(笑)。
ー公演の内容はどうなります?
『Kisah Tropis』の収録曲はもちろん、次作に入れる予定の曲もやります。今回のアルバムは従来のラテンを逸脱したトリッキーなネタがあったり、ポップな要素がありましたが、次回はぐっとジャズ寄りになる予定。その対比や調和を楽しんでもらえれば。
あと、作品は2作目ですけど長く続けてきたバンドなので、全員が曲をこなす状態から曲上で自由に遊ぶ状態になってきています。単純にアンサンブルの質が上がり続けているので、その円熟みたいなものは感じてほしいですね。
当日はアーティストカクテルも出るらしいので、演奏と一緒に楽しんでもらえたらうれしいです。長くて暑い夜になるんじゃないかな。