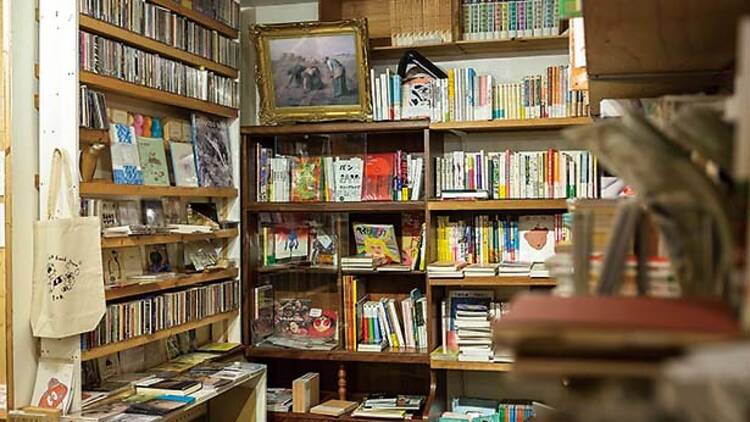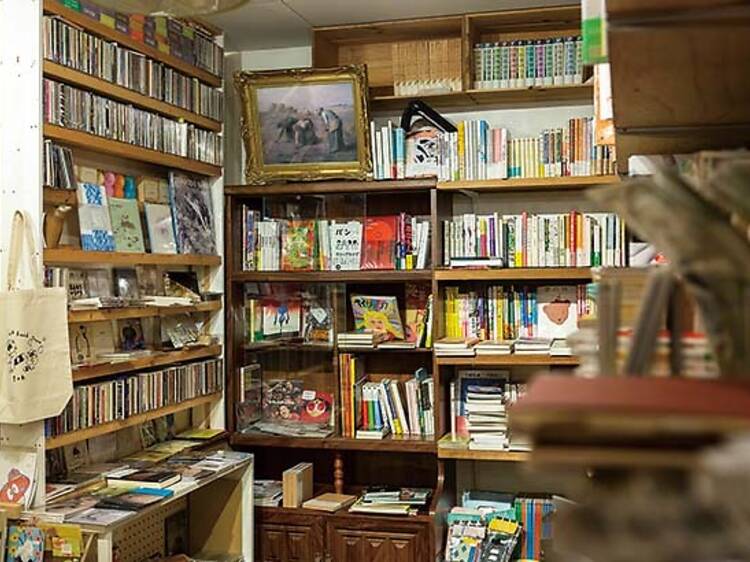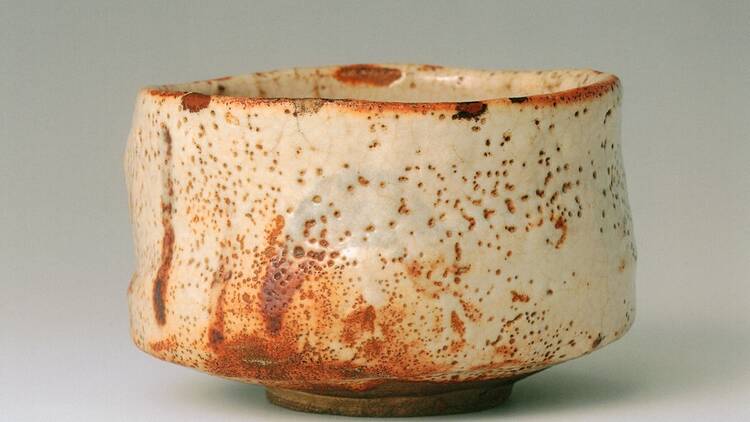国立国際美術館
初めて外観を目にした人は、その奇妙さに仰天するだろう。このユニークな姿をした建物は、「あべのハルカス」なども手がけたシーザー・ペリが設計した。
地上には竹の生命力をイメージしたオブジェだけがあり、展示空間は地下というユニークな構造になっている。
国内外の現代美術を中心とした作品を数多く収蔵し、年に数回、特別展やコレクション展を開催。見せるだけではなく講演会やシンポジウム、ギャラリートークなども積極的に行い、美術への深い理解と普及に努めている。
通常の休館日のほかに、展示替えなどのため臨時休館もあるので注意してほしい。しかし、もし急な休館に当たってしまっても、この建物を見ることができれば十分に来る価値はあるだろう。